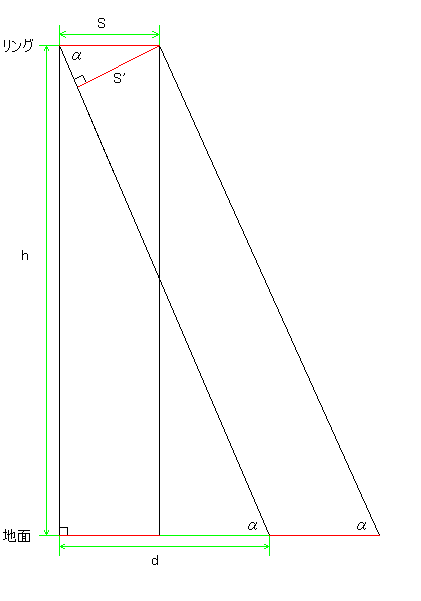別記4 セクター測量方法
(2004/12/29記)
(2005/08/06更新)
1 傾きのないPDC筒がリングに設置されている場合
(2004/12/29)
(2005/08/06更新)
PDC筒の底面にはセクターの方向を示す矢印等のマークが見られますが、セクターの方向は構造上、筒に刺さっている串と平行になっているようです。
この点に着目してここでは、1枚の写真撮影で最大3個のセクターの方向(方位角)を簡易測量します。
方針磁石は、磁性体である鉄塔の近傍では狂いが生じるおそれがあるので、使用しません。
可視の山頂や太陽、直線的な道路など地理的に利用可能な目標物を現地調達することにより、リング中心から撮影位置へ向かう方位角を求めます(表1)。
表1 撮影位置の方位角を把握できる目標物の調達例
例1 | (1)地図上の位置が判明している山頂とリングの中心線が重なって目視できる位置で撮影します。
(2)地図上から、撮影位置の方位角を求めます。 |
例2 | (1)太陽を背にして自分の影とリングの中心が重なる位置(または、太陽へ真正面に向かう位置)で撮影し、撮影時刻を記録します。
(2)国立天文台天文情報公開センター暦計算室のページ(各都道府県の任意の時刻(5分ごと)における太陽の位置(方位角)を参照可)で、撮影時刻における太陽の方位角を求めます(太陽へ真正面に向かう位置で撮影した場合は、180°反対方向になります)。 |
例3 | (1)直線的な道路から直角方向にリングの中心が見える位置で撮影します。
(2)地図上から、撮影位置の方位角を求めます。 |
撮影は、できるだけリングの真下に近い位置に立ち、鉄塔の鉛直方向と画面の縦方向を一致させてから行います。
撮影した写真と地図から、セクターの方位角を求めます(表2)。
| 表2 セクターの方位角の測量例 |
_0.gif) 図1 撮影位置図 |
【撮影位置の確認】 表1の例3の方法により、(ここでは、北西に面する)直線的な道路から直角方向にリングが見える位置を選びました(図2)。 リングから撮影位置へ向かう方位角は地図上、323°になりました。
|
_1.gif) 図2 写真原図 |
【撮影原図作成】 リングと可視のPDC筒の全体を1枚の写真に撮影し(写真1-1)、白いキャンバスに貼り付けます。 写真1-1のうち、PDC筒の底面とPDC筒に刺さっている串が見える部分(写真1-1中、青四角)を拡大し、キャンバスの余白に貼り付けます(写真1-2、写真1-3、写真1-4)。 2枚のリングのうち、全体がよく見えるもの(通常は下段)の縦横の長さを計測します(1024×768pxのディスプレイ使用、印刷時、横64ミリ×縦50ミリ)。
【楕円から円への補正】 リング下段の形状を楕円から円に補正するため、図2の縦幅を(ここでは、128%(64÷50)に)拡大します(図3)。
|
_2.gif) 図3 解析図 |
【図上の角度(みかけ方位角)計測】 写真2-2、写真2-3、写真2-4から、できるだけ串が長く写り込んでいる箇所を見つけ出し、その串に沿って赤線を引き、図の上方を0°とする[みかけ方位角]を計測します(ここでは、293°、28°、151°)。
【方位角の算出】 次の式により、各セクターの方位角を算出します。 [セクターの方位角]=[撮影位置の方位角(ここでは、323°)]−[みかけ方位角(計測値)] 算出された方位角がマイナスになる場合は、360°をプラスします。
【結果確認】 円を描き(ここでは、リング下段で代用)、円の中心から計測値と平行に赤線を引きます。 円の中心から撮影位置の方角(ここでは、みかけ方位角323°)へ青線を引きます。この方角が北です。 残りの3方向(南、東、西)も青線を引きますが、写真は下から見上げたものであるため、東西南北の位置関係は裏返しになります。 解析図(図3)をプリントして頭上に持ち上げて下から眺めると東西南北は裏返しではなくなりますから、現実の方向感覚で結果を確認します。
|
2 傾きのないPDC筒が鉄塔に直接設置されている(リングがない)場合
(2005/08/06)
リングがない場合は、鉄塔の高さ(h)と鉄塔までの距離(d)がわかれば次の近似式により縮小率(S’/S)を求めることができます。
hやdが不明の場合は、多少の誤差は覚悟して傾斜計などで仰角(α)を直接計測します。
以下の作業は、[1]の方法と同様に行います。
ただし、αが小さくなるほど誤差が大きくなりますから、撮影は鉄塔に近い場所で行うのがベターです。
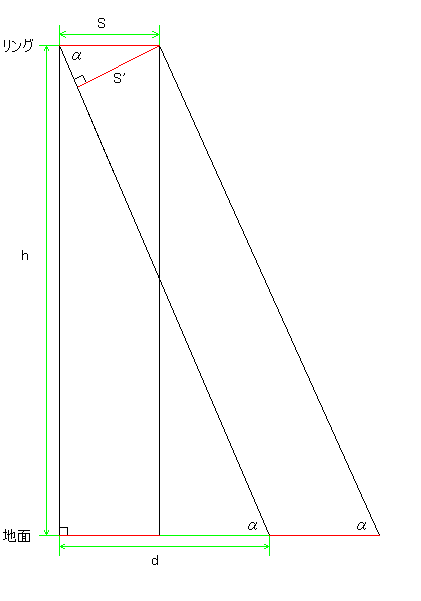 図4 縮小率 |
リングを斜め下から見上げた場合の縮小率(S’/S)は、次のsinαに近似します。 tanα=h/d
S’/S=sinα=sin(Arctan(h/d))
α:仰角
d:鉄塔までの距離
h:鉄塔の高さ
|
3 PDC筒が傾いている場合
(2005/08/06)
筒が傾いていても、筒に刺さっている串がセクターの方向と一致しかつ水平であれば、[2]の方法により測量が可能です。
Copyright (C) 2004-2005 TurtleNeck. All rights reserved.
_0.gif)
_1.gif)
_2.gif)